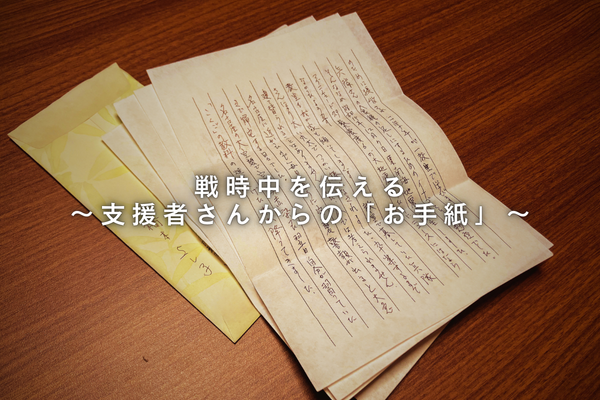フィリピンの子どもたちを応援してくださる方々には、それぞれに異なる想いやエピソードがあります。今日は支援者の橋本よし子さんからいただいたお手紙を、ご本人に許可をいただいて、ご紹介させていただきます。
「高校へ行けなかったことは一生悲しい思い出です。学校へ行きたい子どもが少しでも学校へ行けるようお手伝い出来たら」とおっしゃる橋本さん。橋本さんが体験した戦中戦後の日本の暮らしについて知ることで、フィリピンの子どもたちが今経験している貧困についての理解が深まるかもしれません。
橋本さんからのお手紙(抜粋)
フィリピンの子どもたちの様子を見て、昭和11年(1936年、終戦時9才)生まれの私にもフィリピンの子どもたちと同じような貧困を経験したことを思い出し、70〜80年前の日本もとても貧かったことを知る世代が少なくなった現在、皆さんにお伝えしたくなりました。
昭和18年(1943年)国民学校に入学しました。学用品は極端に少なく、厚紙で出来た筆入れが雨にぬれて壊れてしまい大泣きしました。
昭和19年、父が赤紙によって召集されました。一学年一級の田舎の小さな学校の教室の半分を兵隊さんのために接収され、二学年が一教室で学びました。兵隊さんの食糧の足しにするためのイナゴとりも勉強でした。
そんななか 昭和19年12月7日、東南海地震が発生しました。マグニチュード7.9、最大震度6の大地震だったのに、ニュースにはならなかったようです。教室も我が家も傾いてしまいました。教室で暮していた兵隊さんにより、太い丸太でつっかい棒がなされました。卒業するまで建て替られることはありませんでした。今では考えられません。
名古屋に近かったので毎日のように空襲警報が出ると大急ぎで帰宅する日々でした。名古屋の大空襲で空が真赤に染まった翌日、自分が習っていた「こくご」の教科の焼けこげた本が降ってきました。これは本当に悲しいことで、今でも鮮明に覚えています。
戦後の食糧難は現在の人々には想像も出来ないものでした。 田舎でも農家ではなく、父が兵隊から帰って来るまでは、海水の塩味でたんぽぽやスベリヒユをよく食べました。日本にもこんな戦中戦後があったことを知る人が少なくなってしまいましたので、少しでも知っていただきたいと思いました。
4歳下の弟は何にも覚えていないと云います。昭和14年生まれ位の人々の記憶だと思います。高校へ行けなかったことは一生悲しい思い出となっています。今は自分がその気になれば市民大学や高齢者アカデミーで学ぶことが出来ますので、とても幸せです。学校へ行きたい子どもが少しでも学校へ行けるようお手伝い出来る現在がありがたいと思います。
橋本よし子
橋本さんのお手紙を読んで
アクセス理事長の野田さよです。
日本の戦争が終わってちょうど80年のタイミングで橋本さんのお手紙を拝読し、「当たり前の日常」の意味をあらためて考えさせられています。
安心して眠れる場所があり、食べたいものが選べ、学びたい時に学べた私のこれまでの人生。今になって、それが家族の精一杯の努力のおかげだったこと、そして私たち一家は努力すれば報われるラッキーな環境にあったのだということを実感しています。
今も世界には、最低限の人間らしい暮らしさえままならないまま生きる子どもたちが多数います。その多くが、人一倍努力しても報われるとは限らない環境で生きています。そんな子どもたちやその家族に、これからも「教育の機会」を届け続けたいと、あらためて強く思います。
(了)
【顔の見える教育支援】2025年度子どもサポーター募集中!
フィリピンの新学期は6月16日からスタートします。1日60円からのご寄付で、子どもたちの就学をサポートしませんか?サポートする子どもから顔写真つきのお手紙が届き、お返事を書くこともできます。「娘といっしょに、フィリピンの子どもとの海を越えた交流を楽しんでいます」といった声も届いています。
- 小学生 年22,000円
- 中高生 年36,000円